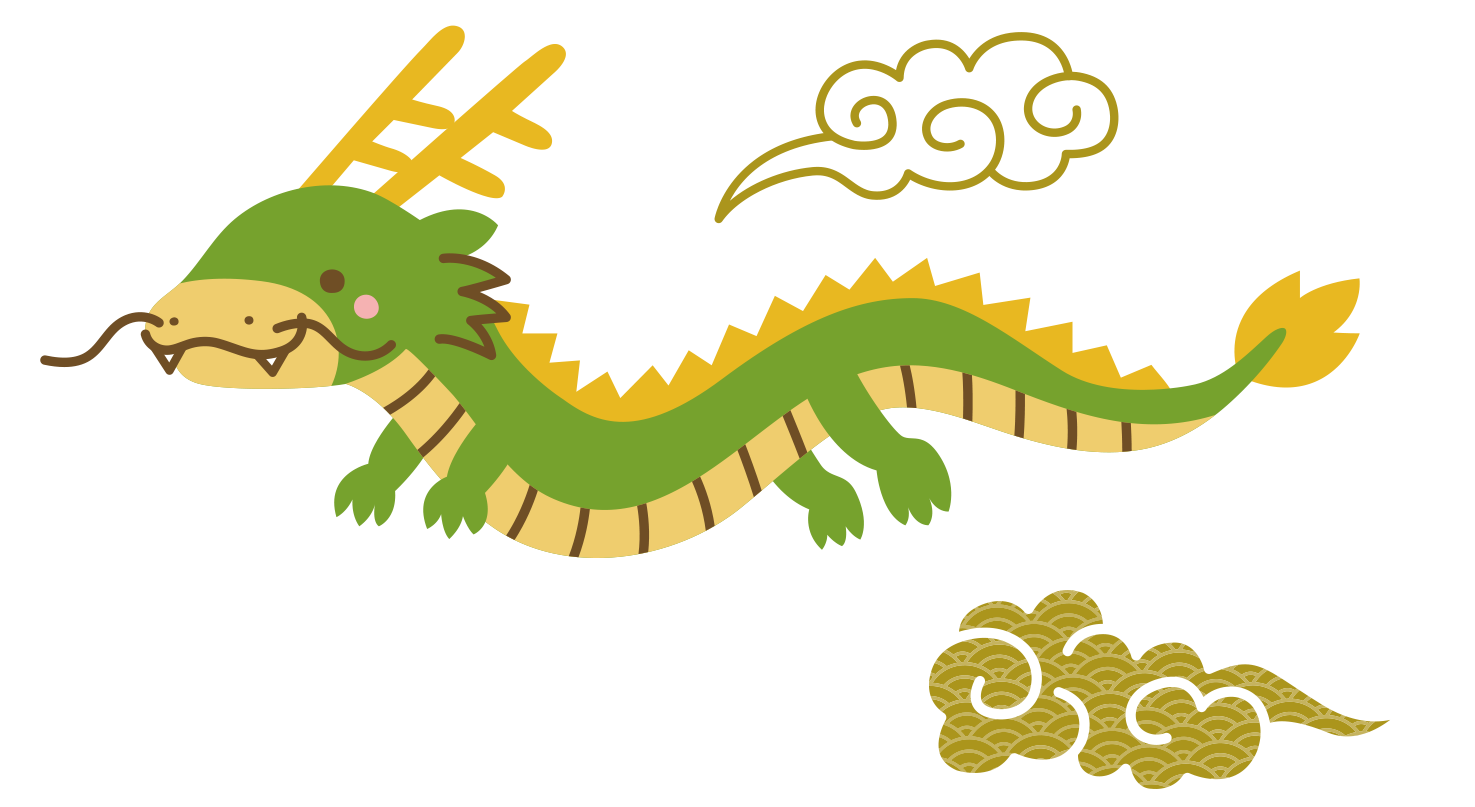アクセスについて
アクセスについて
About 'Access channel'
「アクセス」公式ホームページへお越し頂き有難うございます。アクセスは宮崎県内の障がい者の就労に役立つ情報を中心に全ての障がい者・業界関係者のための就労支援プログラムです。「アクセス」にAccessして頂き、全ての方々のハブとなるようなチャンネル作りを目指して参ります。
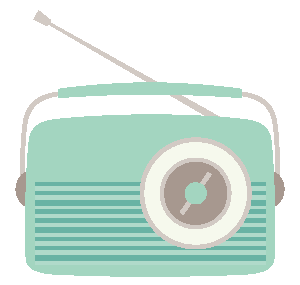
放送時間
『アクセス』は JOY-FM(FM宮崎)にて2021年4月3日土曜日の朝9時半にスタートして、以降毎週土曜日の朝9時 30分からの10分間のチャンネルです!
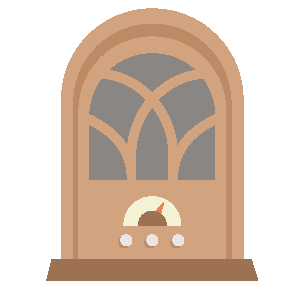
ゲスト
ゲストとして毎回、障がい者就労支援事業所の責任者の方とそこに通って就職された方、通所を頑張ってる方々をゲストにお迎えいたします。
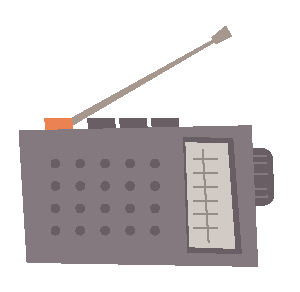
放送内容
今まさに就職を目指している方やこれから利用を検討をしている方、宮崎県内全ての障がいをお持ちの方に送る役立つ情報を伝えるチャンネルです!
パーソナリティー
パーソナリティー
Introducing personality

宮 脇 正
(DJ. KAJIKING)
趣味のカジキ釣りをこよなく愛す福岡県出身の 42 歳。メキシコで開催される世界最大のカジキ釣り大会出場後、FMヨコハマにてカジキングというカジキ釣り専門番組のパーソナリティを1年間務める。宮崎県内7箇所にて障がい者就労支援事業の運営も行っており、閉鎖的になりがちな障がい者就労支援業界をもっと風通しよくまた、障がい者の就労の役に立つ情報発信を!との思いから当番組を企画するに至り番組パーソナリティに就任。
 kajiking55
kajiking55

宮 脇 正
(DJ. KAJIKING)
趣味のカジキ釣りをこよなく愛す福岡県出身の 42 歳。メキシコで開催される世界最大のカジキ釣り大会出場後、FMヨコハマにてカジキングというカジキ釣り専門番組のパーソナリティを1年間務める。宮崎県内7箇所にて障がい者就労支援事業の運営も行っており、閉鎖的になりがちな障がい者就労支援業界をもっと風通しよくまた、障がい者の就労の役に立つ情報発信を!との思いから当番組を企画するに至り番組パーソナリティに就任。
 kajiking55
kajiking55
メインキャスター
メインキャスター
Introduction of Main caster

久 保 修 一 さん
1965年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学法学部政治経済学科中退。日本で初めての障がい者のための労働組合「ソーシャルハートフルユニオン」書記長。会社と対立することが多い労働者側ユニオンという立場でありながら、円滑な職場こそが働く障がい者のためになるとの信念から、会社の苦心や努力にも理解を示し、会社側からも信頼されている障がい者雇用問題のスペシャリスト。著書に『本書を読まずに障がい者を雇用してはいけません!』(労働新聞社)がある。
*ソーシャルハートフルユニオンのウェブサイト

久 保 修 一 さん
1965年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学法学部政治経済学科中退。日本で初めての障がい者のための労働組合「ソーシャルハートフルユニオン」書記長。会社と対立することが多い労働者側ユニオンという立場でありながら、円滑な職場こそが働く障がい者のためになるとの信念から、会社の苦心や努力にも理解を示し、会社側からも信頼されている障がい者雇用問題のスペシャリスト。著書に『本書を読まずに障がい者を雇用してはいけません!』(労働新聞社)がある。
*ソーシャルハートフルユニオンのウェブサイト
準レギュラー
準レギュラー
Introduction of Semi regular

山 下 真 愛 さん
宮崎県の小林市にある「グリーンマーリン」という就労支援事業所と、その近くに新しく出来た「イエローマーリン」という就労支援事業所。この2つの立ち上げを経験された山下さん。この度、沖縄県の八重山列島にある島で石垣市の就労支援事業所「サンマーリン」にマネージャーとして赴任された。現在は就労支援事業所立ち上げのために全国で奮闘されている。

山 下 真 愛 さん
宮崎県の小林市にある「グリーンマーリン」という就労支援事業所と、その近くに新しく出来た「イエローマーリン」という就労支援事業所。この2つの立ち上げを経験された山下さん。この度、沖縄県の八重山列島にある島で石垣市の就労支援事業所「サンマーリン」にマネージャーとして赴任された。現在は就労支援事業所立ち上げのために全国で奮闘されている。
アクセス番組内容
アクセス番組内容
Access broadcast content
 2025 年 5 月 31 日放送
2025 年 5 月 31 日放送再放送(3月15日「令和6年 障害者雇用状況の集計結果2」)
DJ. カジキング
 2025 年 5 月 24 日放送
2025 年 5 月 24 日放送再放送(3月8日「令和6年 障害者雇用状況の集計結果1」)
DJ. カジキング
 2025 年 5 月 17 日放送
2025 年 5 月 17 日放送再放送(3月1日「令和8年、障害者雇用率が2.7%に引き上げ」)
DJ. カジキング
 2025 年 5 月 10 日放送
2025 年 5 月 10 日放送再放送(2月22日「就労継続支援A型事業所でのトラブル」)
DJ. カジキング
 2025 年 5 月 3 日放送
2025 年 5 月 3 日放送再放送(2月15日『「残業・有休・部署異動」の考え方』)
DJ. カジキング
サイト制作担当
サイト制作担当
Site production manager
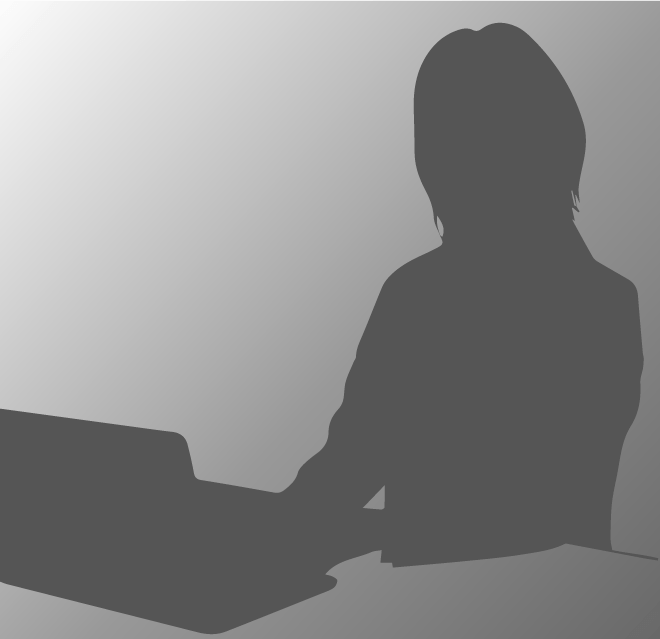
編集担当(N)
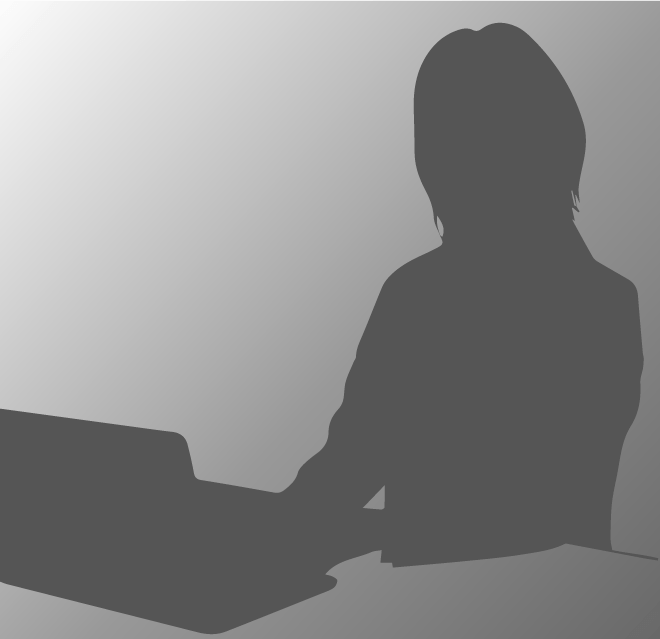
Web担当(N)
プライバシーポリシー
Privacy policy
はじめに
「アクセス」(以下、「当番組」)は、各種サービスのご提供にあたり、お客様の個人情報をお預かりしております。当番組は個人情報を保護し、お客様に更なる信頼と安心感をご提供できるように努めてまいります。当番組は、個人情報に関する法令を遵守し、個人情報の適切な取り扱いをいたします。
1.個人情報の取得について
当番組は、偽りその他不正の手段によらず適正に個人情報を取得いたします。なお、ご相談・お問い合わせに必要な範囲で個人情報を収集する場合があります。
2.個人情報の利用について
当番組は、個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。以下に定めのない目的で個人情報を利用する場合、あらかじめご本人の同意を得た上で行ないます。
・ご相談・お問い合わせに対する回答や確認のご連絡のため
・個人情報を特定しない統計情報に利用するため
3.個人情報の安全管理について
当番組は、取り扱う個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
4.個人情報の委託について
当番組は、個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行います。
5.個人情報の第三者提供について
当番組は、個人情報保護法等の法令に定めのある場合を除き、個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
6.個人情報の開示・訂正について
当番組は、ご本人から自己の個人情報についての開示の請求がある場合、速やかに開示をいたします。その際、ご本人であることが確認できない場合には開示に応じません。個人情報の内容に誤りがありご本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、調査の上、速やかにこれらの請求に対応いたします。その際、ご本人であることが確認できない場合には、これらの請求に応じません。当番組の個人情報の取り扱いにつきまして、上記の請求・お問い合わせ等ございましたら、当番組までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
7.組織・体制
当番組は、個人情報の適正な管理及び継続的な改善を実施いたします。
8.その他の注意事項
当番組が運営するコンテンツや掲載物などからリンクされている第三者のサイト及びサービスは、当番組とは独立した個人情報の保護に関する規定やデータ収集の規約を定めています。当サイトはこれらの規約や活動に対していかなる義務や責任も負いません。
9.個人情報の管理方法の継続的な改善について
当番組は、個人情報の管理方法を見直し、継続的に改善を実施いたします。
10.本方針の変更
本方針の内容は変更されることがあります。変更後の本方針については、当番組が別途定める場合を除いて、当サイトに掲載した時から効力を生じるものとします。
お問い合わせ
Contact
アクセス番組事務局
〒885-0055
宮崎県都城市早鈴町2-8
0986ー51ー6786
info@access-fmradio.com